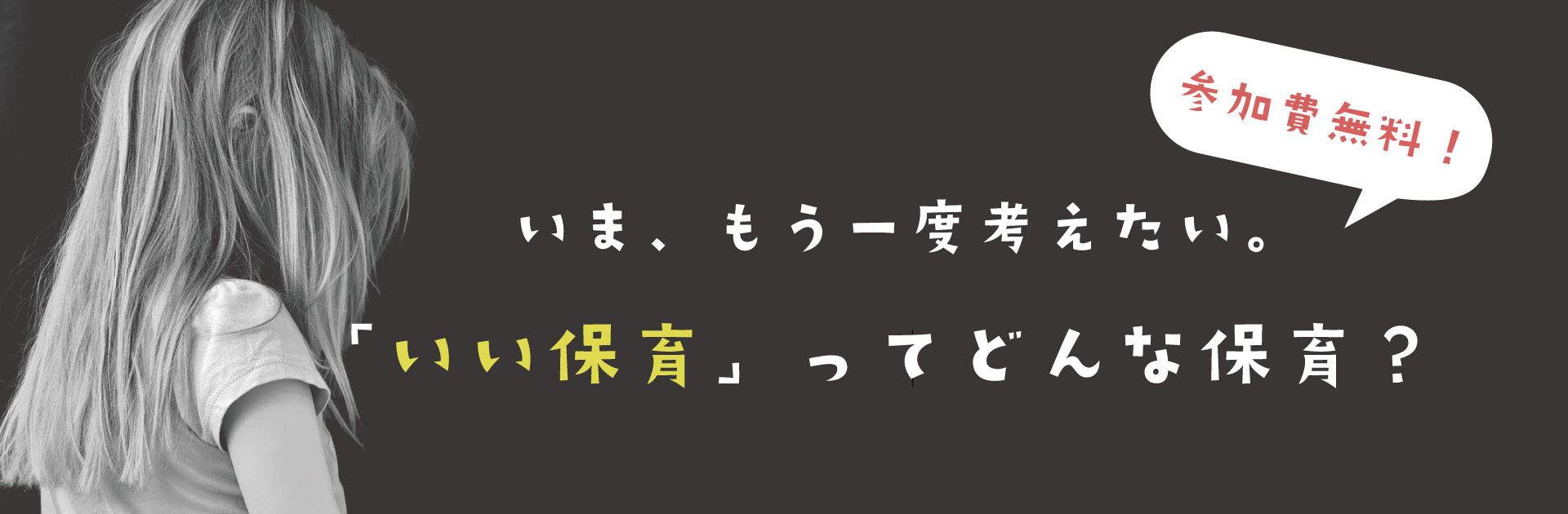誰もが目指しているであろう「良い保育」の実現。
その対極にあるとも言える「不適切保育」が、近年はマスメディアでも取り上げられるようになりました。
子どもたちの笑顔を増やしていくためにできることは何か?
認可保育園の園長として、そして東京都民間保育協会の理事として保育の質に向き合っている曽木書代先生に、お話を伺いました。
※ホイクエンジョイ2024年11月号に掲載した内容です
曽木先生のプロフィール

曽木書代
平成20年より陽だまりの丘保育園の副園長を務め、平成21年より本園と分園の園長を兼任。
一般社団法人 東京都民間保育協会 理事及事務局長として、東京都の保育の向上に貢献している。こども家庭庁、文部科学省など国の保育の質を検討する様々な委員会の委員を務める。
曽木先生のプロフィール

曽木書代
平成20年より陽だまりの丘保育園の副園長を務め、平成21年より本園と分園の園長を兼任。
一般社団法人 東京都民間保育協会 理事及事務局長として、東京都の保育の向上に貢献している。こども家庭庁、文部科学省など国の保育の質を検討する様々な委員会の委員を務める。
曽木先生のインタビュー
正しく知りたい、保育の現場での不適切保育
いま、世間で話題になっている「不適切保育」ですが、「マルトリートメント」と言われることが多くなっております。子育て全般の不適切を意味しますが、保育でも同じように使われることが増えています。真剣に子どもと向き合っている保育士がいらっしゃる現場ほど混乱し、何が不適切で何が適切なのか、そしてマルトリートメントとは何かを、しっかりと知りたい、学びたいと思っている先生が多いのではないでしょうか。
しかし、全国的に見ると確かに、マルトリートメント/不適切保育と言われてもおかしくない悲しい事例があるのも事実です。
最近、不適切保育について研修等に関わる機会をいただくことが増えております。その中で、私たちの園も他人事ではないという思いがあります。自園でも、「子どもの人権について」、「丁寧な保育とは?」を職員皆で研修として話し合っています。また、法人全体での研修で、叱ることの効果の低さや脳のメカニズムなども学んでいます。区で作成した保育の質ガイドラインの中でも、子どもの権利について話し合い、チェックリストを用い、自分たちの保育を皆で振り返ってみました。特に、保育士に伝えるとき、〝わかりやすく〞を大事に伝えています。たとえば、「ビデオに撮られている、園長が見ている時と普段の保育が違っているのであれば、それは注意しなければならない。」と伝えています。人ですので、多少は違う可能性はありますが、そのことを考えてみることは、とても良い研修になります。
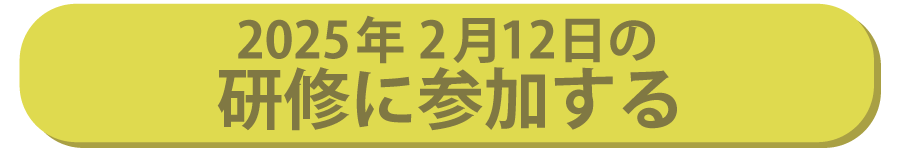
組織や労働環境から解決策を考えていく
子どもが好きで、好きを職業にしている人が多い保育士がなぜ不適切保育をしてしまうのか、そこには何があるのかをより考えていきたいと思っていた矢先、不適切のため監査が入った園の第三者委員をしてほしいと頼まれ、これも何かのご縁だと思い、俯瞰的に課題分析および提言書作成に携わることで、学ばせていただくことにしました。
そこでわかったことの一部をお話しさせていただきます。
まず言えることは、一人の保育士のみが悪く、責められなければならないということではなく、システムとして組織で考えていかなければならないということです。
よく世間では、保育士の低賃金、配置基準、活動のカリキュラムの増加、感染症対策などで保育士にゆとりがなくなっていることも大きな原因ではと言われています。 また、養成校では、虐待は主に家庭で発生するものとし、保育士として自分がしてしまいそうなときの対応は学んでおらず、それも原因なのではとも言われています。
保育士の悩みはほぼ人間関係であり、苛立ち、怒りなどは、負担やトラブルの多発等でより起こりやすくなります。また、子どもをしっかり躾けなければいけないという思い込みで責任感の高い人が陥りやすいと思います。もしかしたら相乗効果で悪化していくのかもし れません。自分の保育を俯瞰的に見ることの大事さを感じます。ストレスのうっぷんなのか、もしかしたら不適切保育だと気づいていない場合や、先輩を見習った結果の園の風土なのか、原因は様々なのかもしれません。
こういったことを防ぐためには、何をしなければいけないのか、園の中で職員同士が組織として一緒に考えていかなければ本当の解決にはならないと思います。
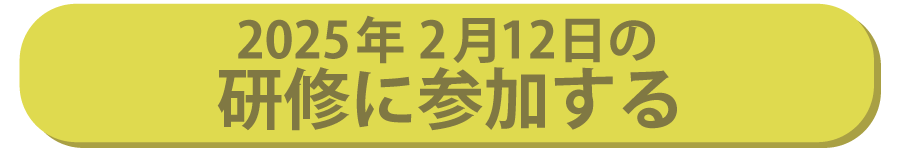
園長を支えるリーダー育成の重要性
先ほど組織で考えていくことが大事とお伝えしましたが、その責任の大部分は園長であり、責任は重く、一番の要になります。しかし、その園長を支える仕組みづくりがないと園長も人ですし、一人で何かできる力には限界があると思います。そのため、リーダー層の職務権限や育成、話し合いの充実が大事であると思います。玉川大学の大豆生田先生の著書『リスペクト型マネジメント』の中でも書かれておりますが、現場を統括する主任の先生やリーダー層との共有や法人の保育理念に沿ってどのような保育を目指しているのかの統一がどれほど大事か、リーダー層が同じ方向を向いていないと改革は難しいと私自身も実感しております。
園では、クラス会議や職員会議のほか、リーダー以上が集まる会議を月1から2回程度、半日近く持っております。時間がそんなに取れないという他園でも、5 分を毎日それぞれが話せる園づくりをした組織は、スムーズな園運営につながっていることをお聞きしました。
忙しいとは思いますが、結局トラブルになると時間を取られます。その前に、保育の振り返りの機会を設けるなどコミュニケーションづくりを心がけることが大事だと思います。
話し合いの時間を多く持つこと、コミュニケーションを密にとり、相手を肯定的に捉え、信頼関係を作っていくこと、職員一人ひとりの言葉を大事にするなど、保育士同士の人間関係と子どもたち同士、子どもと保育士の人間関係は同じようになっていきます。自分の心の在り方を問われているようにも思います。
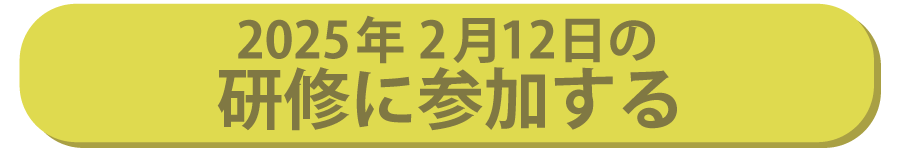
子どもも、保育士も笑顔になる保育を
どこの園でも起こる可能性が潜んでいるマルトリートメント/不適切保育ですが、自分ごとと真摯に考え、また、不適切な保育を考え過ぎて、そこばかりにフォーカスするのではなく、質の高い保育とは?丁寧な保育とは?を考え、そこにフォーカスしていくことが大事ではないかと考えております。皆様の考える質の高い保育とは?丁寧な保育とは?どんなものでしょうか?
子どもが好きで良い保育をしたくて保育士を志した方が多いと思います。そんな中、仕事に追われて楽しくなくなっていませんか?
子どもの声に耳を傾け、思いを寄せ、興味・関心を大事にし、子どもも保育士も一緒に楽しむ保育を本当はしたいと思っている保育士は多いのではないでしょうか。そうすることで、驚くほど子どもも保育士も、生き生きと笑顔が増えていきます。子どもと保育士の心を響き合わせ、かつ冷静に俯瞰的に見ていくことが大事です。子どもたちも自分たち保育士も目を輝かせ、笑顔になっている姿を思い浮かべてみてください。ワクワクしませんか?そのために何をするのか皆で考えていきましょう。
研修の詳細
いま、もう一度考えたい。
「いい保育」ってどんな保育?
子どものために実践したい「いい保育」。そして、目にするとついドキッとしてしまう「不適切保育」。保育士経験が長い方も短い方も、ブランクがある方も現職の方も、保育の質を見つめ直してみませんか?
心に余裕がないときについやってしまいがちな避けたい言動や、子どもの意欲や前向きな心をはぐくむ声掛けなどについてもお話しします。

![]() 講師:曽木書代
講師:曽木書代
東京都民間保育協会 理事及事務局長 /
陽だまりの丘保育園 ひなたの丘保育園 統括園長
 会場:ちよだプラットフォームスクウェア ミーティングROOM 001
会場:ちよだプラットフォームスクウェア ミーティングROOM 001
 アクセス:東京メトロ/竹橋駅‥3b出口より徒歩2分
アクセス:東京メトロ/竹橋駅‥3b出口より徒歩2分
東京メトロ/大手町駅‥C2b出口より徒歩8分
![]() 2025年2月12日(水)
2025年2月12日(水)
14:00~15:30
いま、もう一度考えたい。
「いい保育」ってどんな保育?
子どものために実践したい「いい保育」。そして、目にするとついドキッとしてしまう「不適切保育」。保育士経験が長い方も短い方も、ブランクがある方も現職の方も、保育の質を見つめ直してみませんか?
心に余裕がないときについやってしまいがちな避けたい言動や、子どもの意欲や前向きな心をはぐくむ声掛けなどについてもお話しします。

![]() 講師:曽木書代
講師:曽木書代
東京都民間保育協会 理事及事務局長/
陽だまりの丘保育園 ひなたの丘保育園 統括園長
 会場:ちよだプラットフォームスクウェア
会場:ちよだプラットフォームスクウェア
ミーティングROOM 001
 アクセス:東京メトロ/竹橋駅‥3b出口より徒歩2分
アクセス:東京メトロ/竹橋駅‥3b出口より徒歩2分
東京メトロ/大手町駅‥C2b出口より徒歩8分
![]() 2025年2月12日(水)
2025年2月12日(水)
14:00~15:30
ご予約はこちらから
下記より参加申込みいただくことが可能です。
必要事項をご入力の上、送信ください。