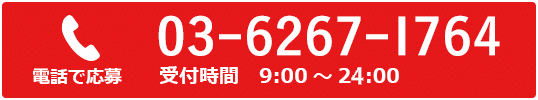ジェノグラムとは?エコマップとの違いは?すぐに保育に活かすコツや描き方を紹介!
- 保育士求人 わたしの保育 TOP
- コラム一覧
- ジェノグラムとは?エコマップとの違いは?すぐに保育に活かすコツや描き方を紹介!
コラム
COLUMN
#日々の保育
作成日 2019/02/09
更新日 2024/05/14
ジェノグラムとは?エコマップとの違いは?すぐに保育に活かすコツや描き方を紹介!

保育の現場で使われるようになった、ジェノグラムという言葉。聞いたことはあるけれど、実際に活用したことがない、そもそも使い方がわからない、という方も多いのではないでしょうか。
ジェノグラムは、利用する中で子どもを取り巻く環境を知ることができ、その理解を深めることができるツールです。また、エコマップも合わせて活用することで、さらに詳しく理解を深め寄り添った保育ができます。現代の子どもの家庭環境は複雑で、その背景を理解しているからこそできる支援やかかわりがたくさんあります。
今回は、ジェノグラムやエコマップの描き方、すぐに保育の中で活かせる方法などをご紹介します。適切な支援として、日々の保育や家庭支援を行なう際に活用していきましょう。
| 目次 |
|---|
ジェノグラムとは?その必要性
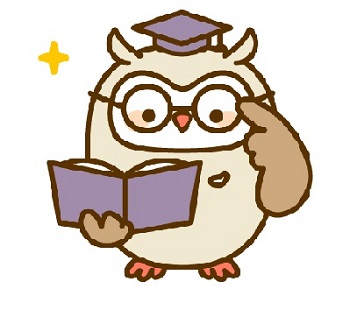
子ども一人ひとりの背景や成長を把握し、寄り添った保育を行なうために効果的なジェノグラム。言葉の意味や、その必要性をご紹介します。
ジェノグラムは家庭環境を可視化するためのツール
ジェノグラムとは、3世代以上の家族や親族の関係を事実に基づいて図式化し、記号で表したもので、いわば家系図のようなものです。これによって、子どもや家族の構成や人間関係を視覚的に理解できます。たとえば、家族や親族の誕生、結婚、離婚から、年齢、性別、兄弟関係まであらゆる面を把握できます。
保育現場では、家族支援を行なう際に重要な人物を見つける資料にもなります。子どもを取り巻く複雑な家庭環境は、言葉の説明だけでは理解が難しい場合もありますが、ジェノグラムで図式化し視覚的に表すことで、家庭状況の把握が容易になります。
ジェノグラムの必要性
子どもや保護者一人ひとりと深くかかわる保育現場。その中には、振る舞いや発言が気になる子どもがいたり、保護者から子どもの成長だけでなくプライベートでの深刻な相談を受けたりと、日常的にたくさんの問題に直面します。それらは簡単に解決できるものではなく、対象者が置かれている立場をまず理解したうえで、効果的な解決手段を講じなければなりません。
しかし、昨今の子どもの家庭環境や取り巻く人間関係は複雑化しており、すぐに解決できない場合も多々あります。そんなとき、保育の現場では環境を把握して適切な支援を行なうために、ジェノグラムを活用します。
ジェノグラムは、元々は障がいを持った方や高齢者の方などを対象として支援に利用されていました。これを保育の現場に取り入れることにより、家庭環境や人間関係の理解をしやすくなります。さらに、その理解も深まるため、より効果的な支援や対処に大いに役立ちます。子どもが気になる行動をとる理由や、家庭が抱える問題とその原因を探るきっかけにもなります。
また、子どもの家庭環境や周囲の人との関係性を事実に基づいて視覚的に把握することで、問題点を探ったり、解決策を講じる必要がある部分を発見したりできます。表面的には見逃されがちな、虐待やネグレクトなどの可能性にも気づくことができます。
このように、ジェノグラムは子どもを取り巻く環境を理解し、今後は誰にどのように働きかけていくかなどを検討するためのツールとなります。そして、今後必要とされる適切な支援を行なうための重要な役割を担っています。
記号を使ったジェノグラムの描き方と解説

では、ジェノグラムは実際に、どのように描けばよいのでしょうか。基本的な、当人を示す描き方から、それぞれの関係性を表す描き方まで解説します。
【基本】性別・本人・対象の図形の描き方
それでは、人物を示す記号について、ジェノグラムの描き方を見てみましょう。
性別
性別は、男性は四角、女性は丸、不明の場合は三角で表します。本人は、二重のマークで示します。

年齢
年齢は、それぞれの性別の記号の中、もしくは記号の下に記入します。

生死状況
亡くなっている場合は、図形を黒く塗りつぶすか図形の中にバツ印を記入します。

妊娠の有無
妊娠している場合は、図形の中に三角を記入します。

【基本】婚姻・親権・居住状況の図形のつなぎ方
次に、人物の関係を示すジェノグラムの描き方を見てみましょう。人物関係のサンプル画像は下にあります。
婚姻関係
妻と夫の図形を横に一本の線で繋ぎます。 子どもがいる場合、線の中央から下に向けて垂直に線を伸ばし、線の先に子どもの図形を繋げます。
別居、離婚
別居中の場合、妻と夫の図形をつないでいる横線の中央を斜め線一本で区切りましょう。離婚している場合、線の中央を斜め二重線で区切りましょう。
同棲
同棲している場合、図形と図形を波線で繋げましょう。
同居
同居している人は、大きく曲線で囲みます。
そのほかに、家族環境を理解するうえで必要な情報は、記号の上に記入します。たとえば入院中であったり、うつなどの精神疾患を抱えていたりなど、把握しておくことで支援のキーになりうるようなことも共有しておくと大きく役に立ちます。
【基本】家庭環境や人物の関係を示すサンプル

- ここからわかること
- 父38歳 母34歳 兄10歳 5歳女児(本人) の4人で同居している
- 父方祖父母は健在
- 母方祖父は亡くなっており、母方祖母は65歳
- 叔母(母の妹)は32歳、離婚している
ジェノグラムとエコマップの違いとは?

ジェノグラムと似ているように思われがちですが、意味はまったく異なるエコマップというものもあります。それぞれの特性を知り、活かすことで、さらに状況を把握しやすくなります。
エコマップは相関関係の地図
では、エコマップとはどのようなものなのでしょうか。
エコマップとは、アン・ハートマン(Ann Hartman)教授が1975年に作った方法です。ハートマンは、ケースワーカーとしてのキャリアをスタートし、家族のメンタルヘルスに関する仕事をしています。そのなかで、家族の複雑な人間関係をアセスメント(評価・査定)し、そこに課題や可能性、解消したいことを見出すため、家族や周りの人々、組織とのかかわりを視覚化するために考え出されました。このように、エコマップはもともと介護の現場のために作り上げられたものなのです。
ジェノグラムは支援対象者の家族関係や親族関係などを事実に基づき記号で表したものですが、エコマップは支援対象者の関係者や関係機関などとの関係性を記号に表したものです。また、事実に基づいたものではなく、本人や周辺の話、客観的な状況判断を元に表します。支援対象者との関係や、事実に基づくかどうかなどでジェノグラムとエコマップとの違いを判断できます。
人が置かれている状況は、刻々と変化しています。そのため、当初作ったエコマップとの相違も生じます。エコマップ作成の際は日時を記入して、状況や支援によって変化が生じたときは、その都度描き変えたり描き加えたりする必要があります。そうすることで、支援対象者の現状を関係施設や関係者と話し合う際や、保育現場での引き継ぎ、共通認識を持ちたい場合などにも活用できます。また関係者だけでなく、支援対象者本人に自身が置かれている立場を客観的に認識してもらうツールにもなります。
このように記録を繰り返すことで支援の振り返りや現状把握だけでなく、保育士としての経験の引き出しにもなり、今後さらに保育の中で活かすことができます。
エコマップの描き方は?
エコマップは正しく活用することで、人間同士の関係を把握する大きな手立てとなります。
それでは、エコマップの描き方を見てみましょう。 エコマップは、支援対象者や保育士、関係施設、友人などを丸で囲みます。その丸と丸を繋ぎ方で、関係性を示します。
普通の関係
細い線で表します。

強い関係
太い線で表します。

弱い関係
点線で表します。

これらは、線が太くなればなるほど強い関係性であると覚えておくとよいでしょう。
対立関係
線に、柵のように縦線を短く数本入れます。

一方が働きかけている関係
働きかけている対象者に向けて、線の先に矢印を付けます。

大切なのは作成すること?それとも作成後?
エコマップは、作成することよりも作成後が重要です。作成したエコマップから支援対象者を取り巻く関係性を把握し、支援を必要としているところや支援内容、対処方法などを考え行動に移していくことが大切なのです。読み取れる内容から、今までとは違う支援方法のほうが効果的なのではないか、実はアプローチすべき人物がほかにいたのではないか、などの気づきを促していくためのツール・手段がエコマップといえます。
対人関係のマップ(エコマップ)の例

- ここからわかること
- 父・母・兄・本人の4人家族
- 父方祖父母と父は対立しており、家族との関係も弱い
- 母方祖母と家族の関係は普通
- 母と叔母の関係は強い
- 叔母は本人に働きかけを行なっている
保育に活かすジェノグラム

事実に基づき、家族構成や人間関係を視覚的に理解できるジェノグラム。これを保育に活かすには、さまざまな方法があります。
ジェノグラムを取り入れる利点とは
保育にジェノグラムを取り入れる方法とその利点は、大きくふたつあります。
ひとつ目として、子どもの気になる行動や、発育上の問題などの原因を見つけ出すきっかけとなることがあげられます。たとえば、虐待の疑いがあったり家庭環境に問題がある場合、明確な事実に基づいた家庭状況を把握することで、原因が見つかりやすくなります。ジェノグラムを利用して把握しているからこそ、ちょっとした変化にもすぐに気づき、何らかの働きかけができます。
細やかに子どもの行動や変化に目を配り、ケアを行なうことは保育士としてつねに求められるスキルです。そのスキルを十分に発揮するためにも、ジェノグラムを取り入れる効果は大きいでしょう。
ふたつ目として、子どもの家庭環境や周囲の関係機関への理解が深まるので、より効果的な支援ができることも利点です。
必要とされている支援は、子どもや家庭、関係者によって異なります。重度の家庭問題を抱えているにもかかわらず、周囲の理解が浅いために必要な支援が行なわれず、さらに問題が大きくなることも考えられます。反対に、過剰な支援によって別の問題が起きることも考えられます。いずれにしろ、しっかりと状況理解をしたうえでの支援は、起きている状況に対してもっとも効果的といえます。
保育に活かすジェノグラムやエコマップを活用した事例
さまざまな活用方法があるジェノグラムやエコマップ。ここでは、保育に活用した事例をご紹介します。皆さんの園ではどんな活用方法があるか、考えてみましょう。
ジェノグラムの変化を活用
ジェノグラムを更新する際に、古いジェノグラムはどうしていますか。過去のものだからと捨てていませんか?また、過去のジェノグラムデータをファイリングした後、見直したことはありますか?
ジェノグラムに変化があるということは、その背景に理由があります。変化の態様も、ある日を境にして起こった劇的な変化なのか、徐々に起こった変化なのか。どのような変化なのか。だれが変化を引き起こしやすいのか。ジェノグラムは情報の宝庫です。
そして、こういった情報は子どもや家族の理解を深める際の味方、手助けとなります。未就学の子どもがいる家庭は、生活にさまざまな変化が起きやすいもの。過去のジェノグラムを探して、その変化を保育に活用しましょう。
- どのような変化があるのか
- 変化の中心にいるのは誰か(変化のキーパーソンは誰か)
- 変化せず安定しているのは誰か
- 変化の大きさはどの程度か(短期間で大幅な変化/少しずつ変化 など)

入り組んだ問題を切り分けて考える際にエコマップを活用する
家庭や地域社会と連携することを求められる保育園。ひとたび問題が起きると、関係者が多いときほど問題が入り組んで複雑に絡み合い、解決まで時間がかかってしまう、などの経験ありませんか?
こんな時は、絡み合っている事象をいくつかのグループに分けて、それぞれのグループにおけるキーパーソン(鍵を握る中心人物)を中心にしたエコマップを描いてみましょう。
子どもを中心としたエコマップでは気が付くことのできなかった”キーパーソンのキーパーソン”がわかったり、グループ間の関係を単純化できるなど、解決の糸口が見つけられるかもしれません。

ジェノグラムを使って保育園でできる保護者支援・家族支援

では、ジェノグラムを保護者支援や家庭支援に活かすためには、どうすればよいのか考えてみましょう。
まずは信頼関係の構築をていねいに
保護者や家庭と保育園との信頼関係をしっかりと築きましょう。ジェノグラムを作成するためには、保護者からプライベートに関するさまざまな情報を聞き出す必要があります。保護者からの信頼を得ていないと、作成するのに必要な情報が手に入らなかったり、表面的な情報しか得られなかったりします。
日々の保育の中で、子どもとだけでなく、子どもを通して保護者とも信頼関係を深めていきましょう。その積み重ねで、信頼とともに情報も得られます。また、あなたの話を聞きます、受容します、という姿勢も大切です。相手に安心感を与えることで会話が広がり、必要な情報を得やすくなります。
信頼関係を築き、情報を得たうえで作ったジェノグラムを参考にしても、問題の原因を見つけ出せない場合があります。この場合は、子どもだけでなくその家族のジェノグラムを作ることで、原因が見えてくることもあります。
一人の対象者にとらわれず、ターゲットを変えて作成することで支援方法がわかる場合もあれば、まったく関係ないと思っていたところに原因を発見する場合もあります。いくつものジェノグラムを重ね合わせてみることで、見えてくる手がかりを突きとめられるでしょう。
そして、ジェノグラムを作成していくうちに、虐待の可能性に気付く場合があります。また、いずれ虐待に発展しそうな状況が見えてくるかもしれません。もし疑いがあるときは、すぐに主任や園長に相談し、児童相談所に通告するなど迅速に対処しましょう。すぐに必要でなくても、のちにジェノグラムが必要な場面に遭遇するかもしれません。ジェノグラムの変化を活用の章で述べた通り、過去に作成したジェノグラムは大いに役立ちますので、保管しておきましょう。
キーパーソンへの働きかけをピンポイントで
ジェノグラムを使って、信頼関係を築き効果的な保護者支援や家族支援を行なうことで、可能になることはほかにもあります。それは、問題を改善できるキーパーソンに対する積極的なアプローチが可能になることです。事実に基づいた内容から状況を把握しているので、支援する側も自信を持って確実な支援方法を選択できるようになるからです。
何事も、本質を追求したうえで見えてきた課題に対し、効果的にアプローチを続けることで現状や問題は変化していきます。キーパーソンを見つけて行なわれる支援は、より効果的で重要なものとなるでしょう。
希望にあった保育士求人を探す
子どもを取り巻く環境理解に活かすベースに

ジェノグラムを保育現場で活かすことで、子どもが置かれている状況を把握し、効果的な支援ができます。そしてその支援は、結果的に子どもの新たな成長のきっかけとなります。最初は作成に時間がかかり、難しく感じるかもしれません。しかし作成することで、必要な手段が明確になります。少しずつ慣れていき、保育に取り入れ活かしてくださいね。
保育の現場は、カリキュラムを通して子どもの保護育成を進めるだけでなく、保護者との関係構築や家庭支援などさまざまな事柄に対応する必要があります。
「わたしの保育」を運営するテンダーラビングケアサービスは保育士の皆さまのスキルスキルアップを応援すべく、無料の保育研修を毎月実施しています。自分のスキルでは不安だ、もっとスキルを上げたい、という方におすすめのさまざまな研修を行なっています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
★保育士向け研修(無料)一覧へ★
★お仕事探しの相談・ご登録は無料ご相談フォームへ★
★お仕事検索はお仕事一覧へ★
 和氣 タイ子 Waki Taiko
和氣 タイ子 Waki Taiko都内の認可保育園にて園長経験7年、保育経験のべ30年以上のベテラン保育士。現在は研修など人材育成に注力。